掲題の映画2つを見たので感想を簡単にメモ。他人にはおススメしづらいが、個人的には良かった。
早稲田松竹という、昔でいうところの2番館で、時折昔の映画を見ることがあるが、今回は、フレデリック・ワイズマン監督の映画を何作品かまとめて上映しているのに気づいた。他にも見たい作品はあったが、3時間を超える長い作品が多く(休憩が入るものもある)、見るための時間調整がうまく行かなかった。今回の2作品はそういう中では比較的短いもの。映画のハシゴなんて、中学生の時以来ではなかろうか。
映画館に貼ってあったそれぞれの作品の紹介を撮ってみた。
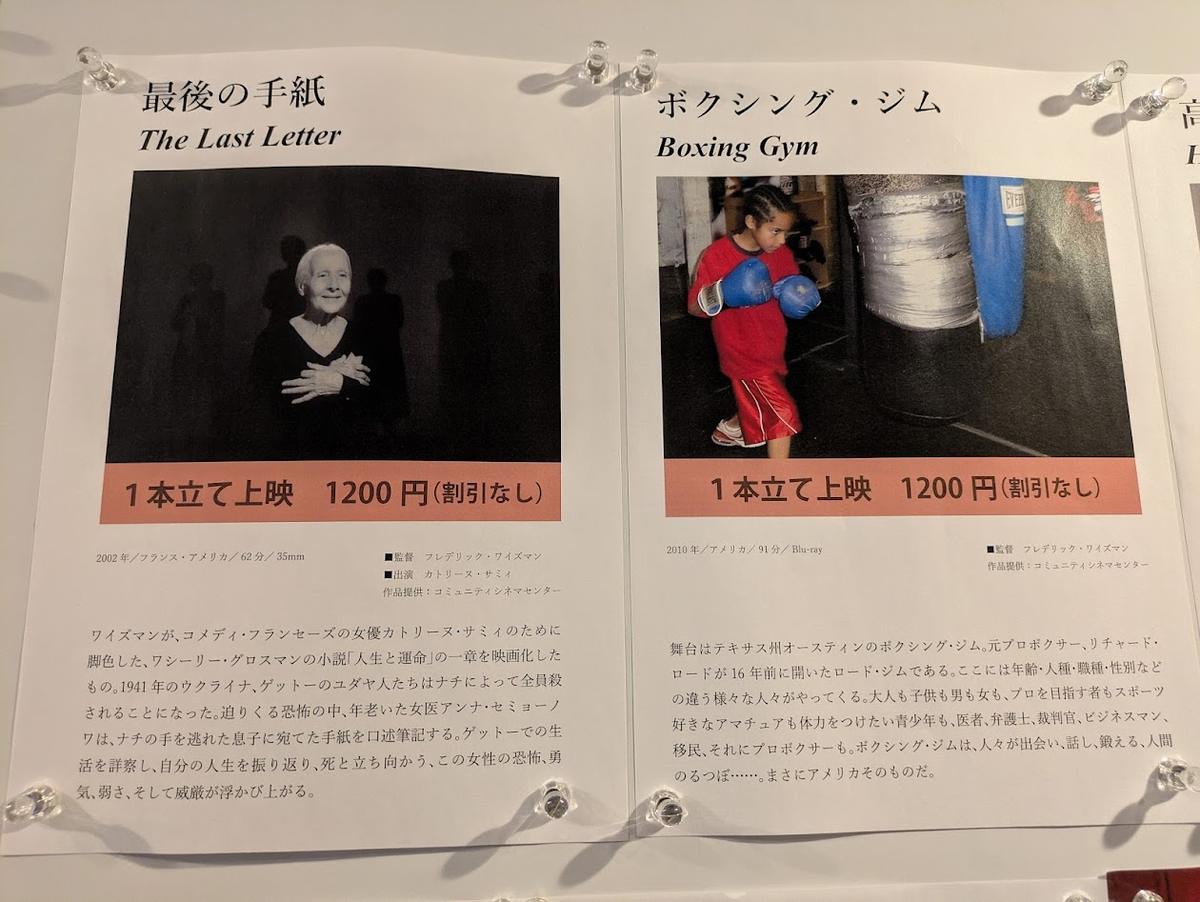
ワイズマンはドキュメンタリーを撮る監督ということになるのだろう。僕が今までに見たのは最近の物ばかりで、「ニューヨーク公共図書館」「ボストン市庁舎」「ニューヨーク・ジャクソンハイツにようこそ」で、最後のものは今回同様に早稲田松竹で見た。特段の説明を付さずに映像を積み重ねていくことで結果的に何かが語られる、という感じの映画を撮っているというのが、これまでの3作品を通じての僕が持つイメージ。必然的に長くなることが多そうで、そうなると映画館でしっかりと没入する形で見たいと思う。また、こういう手法は、合う人とそうでない人が良そうな気もするので、他人様には俄かにはおススメしがたい。
「最後の手紙」は俳優さんが小説の一部を一人芝居で演じるのをモノクロで撮ったもの。ドキュメンタリーというよりも、舞台を映像化した感があり、これまでに見たワイズマンの作品に比べてやや異質な印象を受けた。光と影の扱い方(光を複数方向から俳優にあてて影を複数出すとか)やクローズアップや引き方なども含めて、撮る側の視線が強く感じられて、他とは違う気がした。
俳優が演じるのはナチスドイツに占領されたロシアにいるユダヤ人の女医。収容所に送られ、殺されようとしている中で、ナチの手を逃れた息子に向かって最後の手紙を口述する。ことがここに至る経緯やこれまでの生活を振り返り、迫りくる死に立ち向かおうとしている。極限状況で何とか尊厳を保ちつつ(患者を診て、子供に語学を教えていることがその役にたっているのは間違いないだろう。)、最後の手紙を述べようとしている様子が表現されている。
昨今の状況からすれば、ユダヤ人がこの頃欧州でされた仕打ちを、中東で他の民族にしているかのようにも見えるのが重なってみえ、なんとも言えない気分になるし、ユダヤ人狩りが始まった瞬間に態度を変える隣人たちの様子も、僕たちも、状況に流されて、いつ何時同じことをしないか、という意味で注意が必要と感じたし、そうならないようにしないといけないと感じずにはおられなかった。
「ボクシング・ジム」は、上記の作品とは異なり、TexasのAustinにある元プロボクサーの開いたボクシング・ジムに焦点をあて、そこに集まり、過ごす人々の様子を撮ったものという感じ。ボクシングジムには日本でもアメリカでも行ったことがないが、実に様々な人が来る(という割にアジア系は見なかった気がするが、Texasからだろうか)。ボクシングの習熟度合いも年齢も人種も性別も(若いお母さんが赤ちゃん連れで来ているのも印象的だった)様々な人が来て、それぞれボクシングのための練習をしていて、それぞれに相応に教えているというのも、どういう教育の仕方をしているのかの詳細まではわからなかったが、一定の体系があるようにも見えて、興味深かった。
それに加えて、出てくる人たちがボクシング以外のいろいろなことを話しているのも興味深い。それぞれの生活ぶりやこれまでの人生や生き方についての話、撮影時期の関係もあってか、ヴァージニア工科大銃乱射事件についての話などなど。ろくに知らないはずの相手にそういう話をするのか、という内容もあり、やや驚いた。そういう様子を撮ることで、出てくる人たちの背景を描き出し、そこからアメリカの姿を描こうとしているのだろう。
いずれにしても、ワイズマンは、ドキュメンタリー分野での巨匠であることは間違いがなく、折に触れて作品が上映されているようなので、機会を逃さずに、残る作品も映画館で見ることができればと思う。